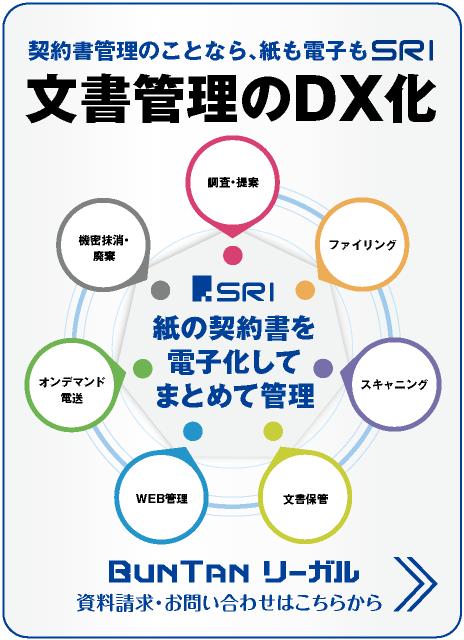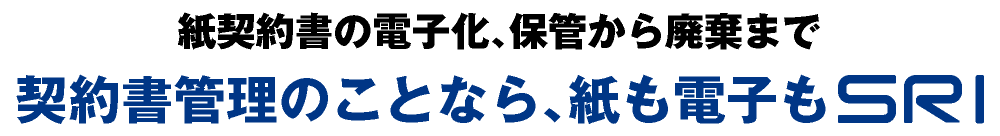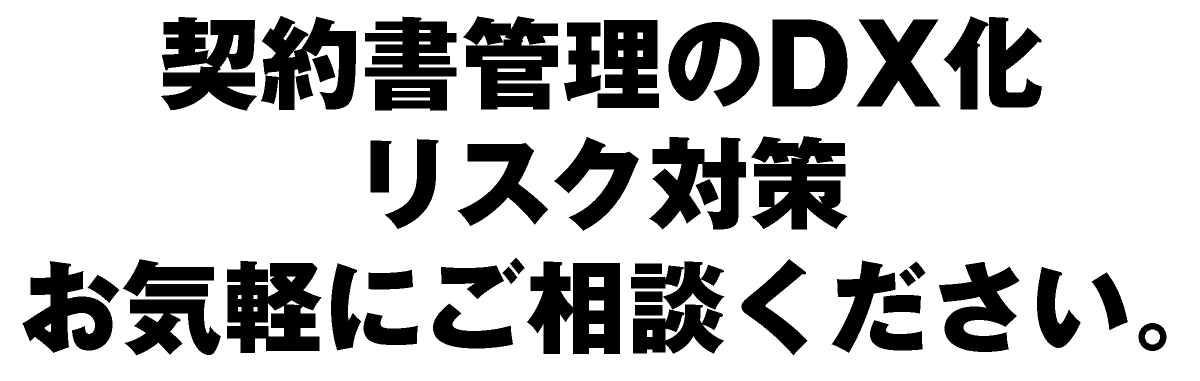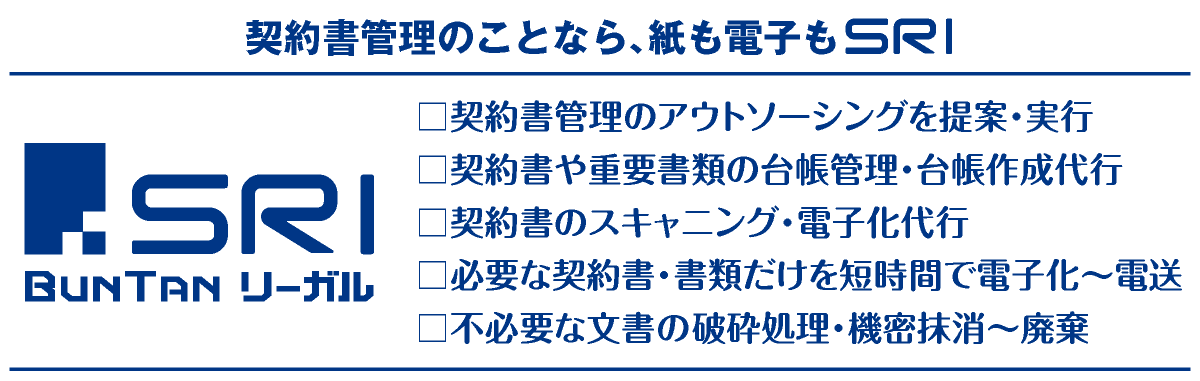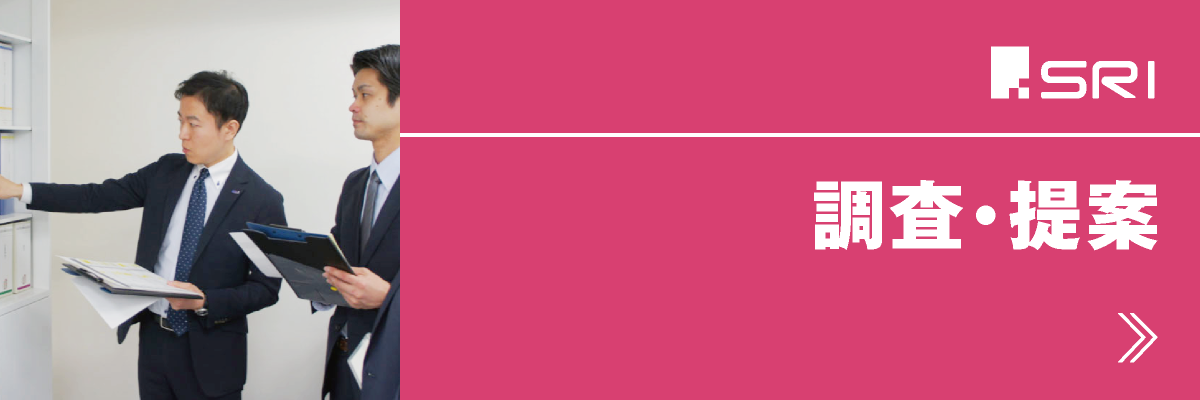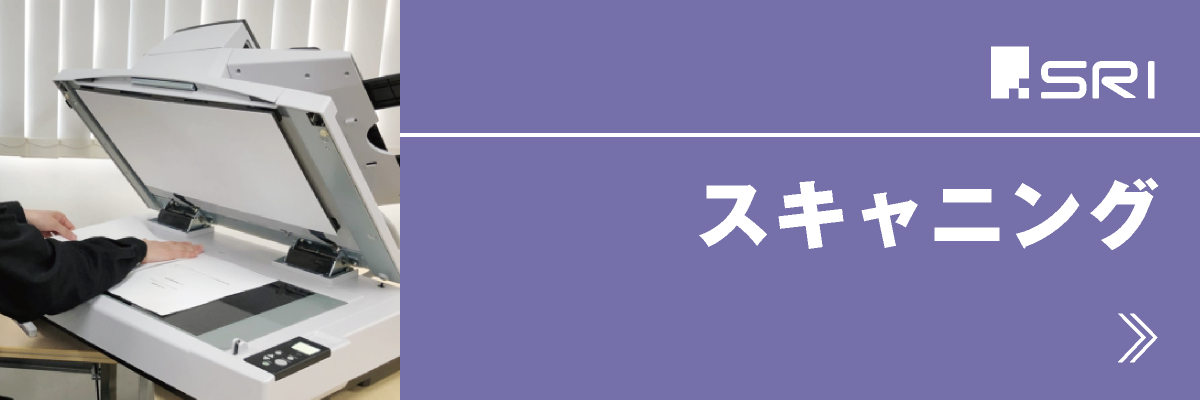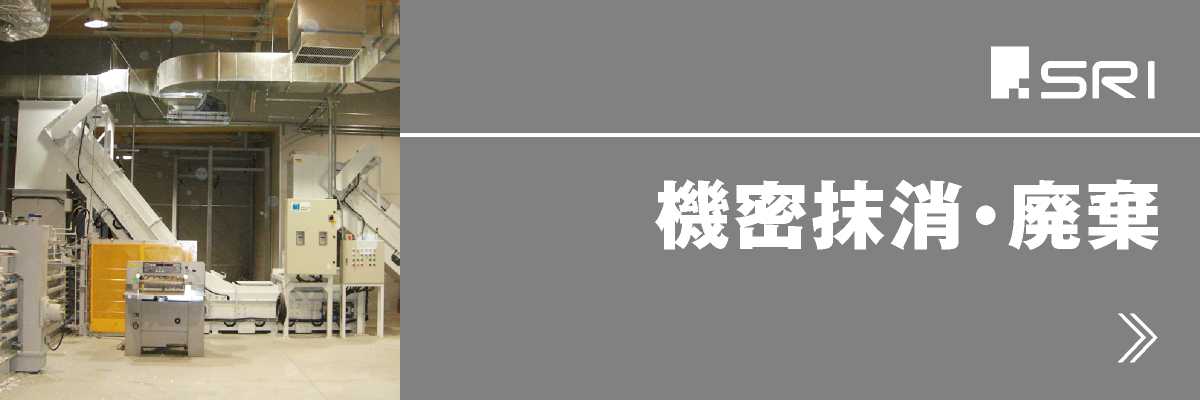東邦銀⾏様
業種:銀行業
社員数:1,001人~5,000人
システム導入以前
システム導入以前の営業店文書管理業務は、全て「人の目と手」という旧態依然の管理手法でした。
これは書類の所在や個人情報の有無が属人的管理であることを意味し、
紛失・誤廃棄のリスクも内在していました。以下、導入前の管理状況です。
●ファイル・テプラなどの用品は各店バラバラで統一性がない
●綴り方・保管ルールも各店バラバラで統一性がない
●文書保存台帳は手書きで、綴る際に規程等で保存期限を確認
●倉庫への保存、処分は、各営業店それぞれの実施で大きな負担
このように、用品・ルールなどの統一性が無く、
その準備や台帳への手書き、倉庫への搬入・処分などを考えても大きな負担がありました。
実際に営業店からの改善要望の声も大きく、営業店業務の平準化、効率化、紛失・誤廃棄リスクの低減を目指すとともに、
営業力の強化に繋げるため、システム化は必要不可欠と判断し、営業店文書管理システムの構築に着手しました。
目指すべき姿
システム構築にあたり、文書のサイクルに沿った「4つのかんたん(綴る・保管・保存・処分)」を実現することが重要です。
スピード感をもった対応をすべく、
「綴る→保管」のかんたん実現を第1フェーズ(システム化)とし、
「保存→処分」のかんたん実現を第2フェーズとしました。
システム化の基本コンセプトである「誰もが”かんたん”に使えることが最良の仕組みである」ことを具現化するため、
そのひとつとして、従来のバーコードと比較して読み取り速度の速い新技術「カラービット」を採用し、
その読み取り機器としてタブレット端末を使用することとしました。
※カラービットはビーコア株式会社の登録商標です。
開発の基本理念・ベンダー選定
今までのように営業店の裁量に任せた綴り込みを継続すれば今は楽ですが、
これからも文書保存台帳の手書きや情報資産台帳の手入力といった負担が残ったままになります。
今回、文書管理システムの導入・開発にあたり、基本理念として掲げたのは「全店統一の基準で綴る」です。
この基本理念を実現することによって、「ファイルに綴じたまま保存できる(製冊不要)」、
「タブレットでファイルラベルを撮影するだけで台帳を自動作成する」ことができ、
手作業・手管理の負担を大幅に軽減することができます。
すなわち、当行は「将来的な価値」を重視することにいたしました。
そのため、企業規模・過去の成功・現状維持(パッケージ販売)に捉われずにベンダー選定を行った結果、
将来価値の創造へ一緒に取り組んでくれるパートナーとして、SRIを選びました。
ファイル基準の策定
今までのようなファイルへの綴り込み作業は、統一したルールが無いが故に綴り込みミスによる誤廃棄リスクを伴うことや、
保存年限の判断に時間を割くようなことがありました。
全てが1帳票=1ファイルであれば綴り込みに迷うことは無くなりますが、
大量のファイルが必要になり、スペースの問題もでてくるので現実的ではありません。
これに対応するため文書管理コンサルティングを導入し、
SRIと共に複数の書類を効率よくファイルに綴り込む基準を策定しました。
その結果、「複数帳票=1ファイル」としていくわけですが、
この基準に沿ったファイルラベルを毎年全店へ配付する事にしました。
(初年度分のみファイル貼付・全営業店配付をSRIへ依頼)
このラベルには、どの書類を一緒に綴じればよいのか明確になっています。
また、保存期限も明確に設定されているので、
担当者は業務経験の長さに左右されず、誰でも同じようにファイリングする事が可能となります。
これが当行の目指す、「業務経験等に左右されない手順の定着(作業平準化)となります。
新たな技術を文書管理に導入
ファイル基準の策定と同時に、ファイルラベルの読み取りをより効率的なものにするため、
従来使われているバーコードとハンディ端末ではなく、
一括読み取りが可能な新技術”カラービット”を採用し、その読み取り端末はタブレット端末としました。
カラービットは、タブレット端末の動画カメラで一括読み取りができるので、
ハンディターミナルのように一つ一つファイルを読み取らなくても良いことが最大の利点です。
また、元々別の施策でタブレット端末の導入予定があったこともあり、
これを文書管理にも応用することでその導入価値を上げることにもなりました。
タブレット端末によるファイルラベルの読み取りができることによって、
文書保存台帳、情報資産台帳が自動作成され、営業店の事務負担は大きく低減されます。
※カラービット製品はバーコード、ICタグなど自動認識システムを手掛ける株式会社サトーより提供を受けています。
第2フェーズの取り組み
平成26年4月に第1フェーズが全店稼働を迎え、これから第2フェーズの取り組みが始まります。
この第2フェーズでは「保存→処分」のかんたんを実現していくわけですが、
第1フェーズのシステム化や管理規程の見直しを考慮し、将来的な文書量を推測したうえで、
県内複数の倉庫を1箇所に集中化するのか、
外部の専門管理会社へ委託した方が良いのか、セキュリティ・利便性も含め検討を進めていきます。
ユーザーごとの開発計画に合わせて段階的に進めれることや機能追加など、
柔軟な対応ができることもSRIの利点であると考えています。
※導入事例に掲載されている法人名、個人名、コンテンツは、お客様より許可いただいた上、構成・公開しています。
※既出公開されている導入事例記事を再編集したもので、在籍・部署・肩書き等は、インタビュー当時のものです。